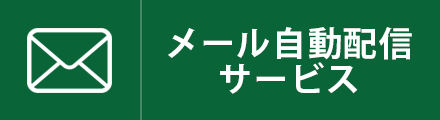これまでの受賞作品(詳細)
- 人材開発事業
- 国際開発研究 大来賞
- これまでの受賞作品(詳細)
| 受賞者/選評執筆者の所属・役職等は、出版/執筆時のものです。 |
第29回受賞作品(2025年度)
牧田 東一 著
『リベラルな帝国アメリカのソーシャル・パワー
-フォード財団と戦後国際開発レジーム形成』
(明石書店 2024 年)
著者略歴
牧田 東一(まきた とういち)
1978年 東京大学教養学部基礎科学科卒
1980年 東京大学教養学部教養学科文化人類学分科卒
1980年~2002年 財団法人トヨタ財団国際部門プログラム・オフィサー
インドネシア、マレーシア、ネパール、ベトナム、カンボジア担当
2017年 東京大学大学院総合文化研究科(国際関係論)修士課程入学(仕事と兼務)
2002年 東京大学大学院総合文化研究科(国際関係論)単位取得退学
2002年 桜美林大学国際学部准教授
2006年 同教授
2006年 学術博士
現在 桜美林大学リベラルアーツ学群教授、サービスラーニングセンター長
受賞者のことば・著者略歴・主要業績
第28回受賞作品(2024年度)
汪 牧耘 著
『中国開発学序説 - 非欧米社会における学知の形成と展開』
(法政大学出版局 2024 年)
著者略歴
汪 牧耘(おう まきうん / WANG Muyun)
東京大学東アジア藝文書院特任助教。中国貴州省生まれ。2018年法政大学大学院国際文化研究科修士課程修了(国際文化)。2022年東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了(国際協力学)。東京大学東洋文化研究所特任研究員を経て、2024年4月より現職。都留文科大学、国際基督教大学非常勤講師。専門は開発学、対外援助研究。「より良い生」をめぐる感覚、記憶や言説の知識化に関心があり、中国や日本、そして東南アジアをフィールドとして、国際開発の学問的な系譜をドキュメント分析と現地調査から浮き彫りにすることを試みている。
主要著書・論文
第27回受賞作品(2023年度)
寺内 大左 著
『開発の森を生きる -インドネシア・カリマンタン 焼畑民の民族誌』
(新泉社 2023 年)
| 選評(政策研究大学院大学教授 大野 泉) | |
| 本書は、カリマンタンで進むアブラヤシ農園開発や石炭開発に対し、現場で開発問題に直面する焼畑民がどのように生きようとしているかを、現地の人々の「生計戦略・生計論理」の視点から考察した大作である。ブヌア人の村(BS 村)に1年2 ヵ月滞在して実施した焼畑民との対話、家計調査、焼畑調査、自然資源利用調査、労働形態や贈与関係等の丹念な現地調査は、収集・分析されたデータの価値、および手法の学際性という点で高い学術性をもつ。研究者の観察の緻密さ、そして気迫に圧倒された。 グローバル化が進み、多国籍企業が国境を超えて途上国で経済活動を行うことが当然となった今、影響をうける現地の人々の土地、環境、人権の保護など、倫理性ある企業行動はビジネスの鉄則になっている。また「持続可能な開発目標(SDGs)」の時代において、若い起業家たちがNGOと連携して途上国・地域の社会課題解決のためのソーシャルビジネスへの関心も高まっている。 こうした時代に、本書が放つメッセージは斬新だ。ここに描かれている焼畑民は、多国籍企業がビジネスを展開する際、決して一方的に搾取される、脆弱な人々ではない。焼畑民は、開発を受入れるか否かという二者択一ではなく、試行錯誤を重ねながら様々な生計手段を組合せて「柔軟性」と「自立性」を確保し、したたかに生計戦略をたてている。 本書の最大の魅力は、開発について二項対立的な考えや、企業、NGO、開発専門家等の外部者が重視する価値基準ではなく、焼畑民の現地の暮らしの論理を軸に独自の分析枠組を構築し、人々に寄り添って徹底的に調べあげた点にある。さらに2000 年以降、インドネシア政府が推進した民主化・地方分権化により住民が主体的に意思表示できるようになったことや、インフラ整備がBS 村の開発にもたらした変化についても具体的に描いている。 企業による大規模事業が及ぼす影響について、現地の人々の暮らしの視点でみると、外部者が重視する基準とは異なる解釈(ズレ)がありえる。本書の分析と洞察は、開発のあり方を考える際の重要な指針となろう。その意味で、本書は学術性のみならず実践面でも示唆に富み、国際開発研究大来賞にふさわしい作品である。 |  |
著者略歴
寺内 大左 (てらうち だいすけ)
筑波大学人文社会系准教授。1983年大阪生まれ。2006年信州大学農学部卒。2014年東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程単位取得退学。博士(農学)。東京大学大学院総合文化研究科・日本学術振興会特別研究員PD(2013~2016年)、京都大学東南アジア研究所・研究員(2016~2017年)、東洋大学社会学部・助教(2017~2021年)。2021年4月より現職。専門は環境社会学、インドネシア地域研究、国際開発農学。インドネシアの農村地域をフィールドとして、地域住民の生活の実態を明らかにし、開発や森林保全のあり方を検討する研究を行っている。最近ではインドネシアで生産されるグローバル・コモディティをめぐる国際的な動き(例えば、国際資源管理認証制度やフェアトレード、デューデリジェンス)が、インドネシアの地域住民や企業を含む多様なアクターのポリティックスに、どのような影響をもたらしているのかを調査している。
主要著書・論文
「グローバル・コモディティの環境社会学」『環境社会学研究』27号(2021年)。「パーム油認証ラベルの裏側」『誰のための熱帯林保全か』(笹岡正俊・藤原敬大編、新泉社、2021年)。「東カリマンタンの石炭開発フロンティアにおける焼畑社会の再編」『東南アジア研究』58巻1号(2020年)。「焼畑民によるアブラヤシ農園開発の受容」『東南アジア研究』55巻2号(2018年)など。
第26回受賞作品(2022年度)
工藤 晴子 著
『難民とセクシュアリティ -アメリカにおける性的マイノリティの包摂と排除』
(明石書店 2022年)
| 選評(東洋英和女学院大学名誉教授 ケア・インターナショナル・ジャパン副理事長 滝澤 三郎) | |
| 性的指向やジェンダーを理由として迫害される性的マイノリティの存在は長らく不可視化されてきたが、彼ら・彼女らの保護の問題は2000年代に入って注目を集めるようになり、UNHCRなど国際機関もその重要性を唱え、対策を練るようになった。 本書は、世界で最も多くの難民を受け入れているアメリカにおける「性的マイノリティの難民」の問題を、国際社会学/移民研究の方法で、歴史的、政治的、社会的な大きな文脈の中で読み解いたものである。筆者は、これまでの難民研究が法的な難民認定問題に留まりがちであり、庇護や難民政策の政治的かつ歴史的な特性を見逃しているという批判的視点と、難民と移民は二分化できるものではなく連続線上に位置する相対的な存在(庇護と移住のネクサス)であるとの認識から研究を進めた。 国家は権力的な国境管理によりその時々の政治が望まない人々を「排除」しようとする。支援側は難民条約の柔軟な解釈でより多くの難民 を「包摂」 しようとする。性的マイノリティの難民申請者は、この二つの波がせめぎ合う中で、手探りしながらも主体的に信憑性のある物語を作り上げ、それに自らを同一化し、ついには難民認定を得る。メキシコとアメリカの間を長年に亘って行き来していた「移民」が、支援者や難民審査官との対話の中で「難民」として自覚していく過程、いわば「社会的に構成された難民になる」プロセスはとても興味深く、それはまた「難民とは誰か」という問いを改めて提示する。 作者は、UNHCR勤務の経験もあり、理論に走らない実践者としてのバランスの取れた眼を持っている。その点でも本書はパイオニア的で独自性のある研究書である。 日本では性的マイノリティの難民の問題はまだ広くは認識されていないが、2018年にはレズビアン女性に初めて難民認定がなされたほか、入管庁が現在策定中の「難民認定ガイドライン」も、性的指向、ジェンダーによる迫害の認定についての初めての指針を示している。 そのタイミングで出された本書は、その豊かな表現力と相まって、日本の難民研究の最先端を行く高い水準の作品であると共に、難民審査担当者や支援者にとって実践的な価値も持つ。本書はまさに国際開発研究大来賞にふさわしい作品であると言えよう。 |
 |
著者略歴
工藤 晴子 (くどう はるこ)
神戸大学大学院国際文化学研究科講師。博士(社会学)、修士(社会学、難民・強制移動研究)。専門は国際社会学、ジェンダー/セクシュアリティ、難民・強制移動研究。UNHCRエジプト・カイロ事務所、トルコ・ガジアンテップ事務所にて性とジェンダーに基づく暴力の予防や対応を中心とした難民支援に携わる。2021年より現職。
主要著書・論文
「難民・避難民の移動と支援におけるジェンダーに基づく暴力」『トラウマティック・ストレス』20号 (2022).「クィアとしての難民とことば」『ことばと社会』16号(2014). 「セクシュアリティとトラウマの動員-米国サンフランシスコ・ベイエリアにおけるメキシコ出身クィア庇護希望者のナラティヴ構築」『年報社会学論集』27号(2014).
第25回受賞作品(2021年度)
下條 尚志 著
『国家の「余白」─メコンデルタ 生き残りの社会史』
(京都大学学術出版会 2021年)
| 選評(東洋英和女学院大学名誉教授 ケア・インターナショナル・ジャパン副理事長 滝澤 三郎) | |
| 「国家の余白」 ~ このタイトルにひかれて本書を読んだ読者は多いのではないか。著者が定義する「国家の余白」とは、「大都市に近く一定の人口を持ち農業生産が行われているにも関わらず、国家の力が及ばないままローカルな秩序が保たれている空間」だ。 著者は、メコンデルタ南部の多民族社会フータン村に1年4か月住み込み、役人から庶民までを対象に聞き取り調査をする中でそのような空間の存在に気付いた。インドシナ戦争、ベトナム戦争、社会主義、ドイモイ、ベトナム・カンボジア国境紛争など大きな歴史のうねりの中で、「国家が介入しにくい空間」が存在し、人々はそこでローカルな秩序を作り上げ、生き残りを図ってきたのだ。動乱の中でしたたかに生きる人々の心理と行動を、文献レビューとオーラルヒストリーの手法で描き出した本書は、大河小説の趣すらある。 「国家の余白」という概念には新規性があり、その視座からは新しい光景が見えてくる。ソマリアでは政府の権力の及ぶ範囲は首都周辺の数平方キロに限られ、国家のほとんどが「余白」だ。アフガニスタンでも、軍閥が割拠して紛争が続き、政府の権力、サービスはカブール近郊に限られ、「国家の余白」で暮らす人々は、国内避難民を含め、はるかに多い。そのような空間で人々がいかに生きているかを理解する上で、本書のアプローチは役立つ。 「国家の空白」地帯は「閉ざされた空間」ではなく、流動性の高い地帯でもある。人々は紛争を逃れて外国に難民として流出することもあれば、経済的機会を求める移民が流入することもある。「国家の空白」は移民、強制移動研究にも新しい視点を提供する。 このように本書は独自の視座に立った研究書で、学術的な価値が高いが、実践的価値もある。援助の計画と実践において「国家の余白」を否応なしに意識せざるを得なくなる。国家の権力が及ばない、流動性の高い地域への外部からの支援はどうあるべきだろうか?それに対して本書はヒントを提供する。 本書は大著だが、文章は読みやすく、写真などによって現地の様子もわかり易い。「国家の空白」という主題を繰り返すことによって著者の主張が可視化されている。研究者だけでなく、実務家、大学院生にも良き参考文献となるだろう。大来賞にふさわしい、若手研究者による力作であって、外国にも紹介されるべき作品である。 |
 |
著者略歴
下條 尚志 (しもじょう ひさし)
神戸大学大学院国際文化学研究科准教授。1984 年東京都生まれ。2007年慶應義塾大学経済学部卒。2015 年京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士後期課程研究指導認定退学。博士(地域研究)。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科研究員(2015 〜2016年)、京都大学東南アジア地域研究研究所機関研究員(2016 〜2017年)、静岡県立大学大学院国際関係学研究科助教(2017 ~ 2021年)。
主要著書
「ベトナム南部メコンデルタ」共編著『東南アジア上座部仏教への招待』風響社、2021.10。「ベトナム―カンボジア国境の越境移動をめぐるローカルな政治―冷戦終結後メコンデルタのクメール人越境者とベトナム国家」『アジア・アフリカ言語文化研究』95 号、2018.3。『戦争と難民―メコンデルタ多民族社会のオーラル・ヒストリー(ブックレット≪アジアを学ぼう≫ 42)』風響社、2016.10。“Local Politics in the Migration between Vietnam and Cambodia: Mobility in a Multi-Ethnic Society in the Mekong Delta since 1975.” Southeast Asian Studies 10 (1), pp.89-118, April 2021. “From “Ideal Social Model” to Reality: Vietnamese Studies in Japan.” The Journal of Vietnamese Studies 16 (1),pp.4-47, February 2021.
下村 恭民 著
『日本型開発協力の形成 ─政策史1・1980年代まで シリーズ「日本の開発協力史を問いなおす」1』
(東京大学出版会 2021年)
| 選評(法政大学名誉教授 絵所 秀紀) | |
| 本書は、「日本の開発協力の歴史を政策決定、意思決定の歴史として描く」ことを目指したものである。筆者をおいて、このテーマにこれだけの情熱を持って取り組むことのできる人を思い浮かべることができない。欧米諸国が主導してきた「国際開発規範」とは大きく異なるわが国開発協力の「異質さ」を、途上国側のイニシアティブを尊重する「顧客志向型」開発協力モデルとして描き出した。今後、本書に対する異論や補論、さまざまなレベルでの批判や逆にデータ等を補強した研究が生み出されることが期待できる、刺激的な作品である。例えば、「武器輸出なきトップドナー」になりえたとする議論や、日本の開発協力が追求してきたのは「ODAによるインフラ整備・直接投資を通じた輸出工業化支援・輸入促進(市場開放)の三位一体型」開発協力による発展途上国の「経済自立」=「援助依存からの卒業」であった、等の議論は蒙を開かれる思いがすると同時に、なお一層議論の余地のある仮説であると思われる。 本書は、わが国の開発協力政策の形成と展開を戦後史という文脈の中に位置づけて描き出した初めての試みであり、この点に本書の意義と魅力がある。戦後史の中に位置づけたことによって、わが国の開発協力を一個の歴史的個性をもった事例として描きだすことに成功した。今後、長きにわたって参照基準となるような自画像的な作品である。また逆説的ではあるが、そのことによってDACを軸に形成されてきた「援助(開発協力)」のあり方を相対化して再検討する可能性がうみだされた、あるいは開発協力の多様なあり方(オールタナティブ)の可能性を示唆する作品になったといえよう。 なお本書は、「被援助国であった日本が世界最大の援助国となるまでの期間を対象」としたもので、1980年代末までをとりあつかっている。「1990年代以降」をとりあつかう『最大のドナーの登場とその後―政策史2』の出版が予定されており、その出版が待ち望まれるが、本審査委員会では本書をそれ自身で完結した作品として評価した。筆者も本書の「あとがき」で、「険しい道を何とかゴールにたどりつくことができたいま」と記しており、本書を完結した作品としてみなしていると思われるからである。最後になったが、このようなすぐれた作品を世に送り出してくれた筆者に心からの敬意を払いたい。 |
 |
著者略歴
下村 恭民 (しもむら やすたみ)
法政大学名誉教授。1940 年生まれ。慶応義塾大学経済学部卒、コロンビア大学MBA。大手メーカー勤務を
経て海外経済協力基金(現・国際協力機構)に入り、インドネシア、インド、タイに駐在、経済部長。国際協力銀行監事。埼玉大学教授。政策研究大学院大学教授、法政大学教授、法政大学大学院環境マネジメント研究科長。
主要著書
『開発援助政策』日本経済評論社、2011。『国際協力』共著、有斐閣、第 2 版:2009。『開発援助の経済学』共著、有斐閣、第 4 版:2009。『中国の対外援助』共編著、日本経済評論社、2013。『貧困問題とは何であるか「開発学への新しい道」』共編著、勁草書房、2009。『ODA 大綱の政治経済学』共著、有斐閣、1999。Japan’s Development Assistance: Foreign Aid and the Post-2015 Agenda , (eds.) Palgrave Macmillan, 2016. A Study of China’s Foreign Aid - An Asian Perspective , (eds.) Palgrave Macmillan, 2013. The Rise of Asian Donors: Japan’s Impact on the Evolution of Emerging Donors, (eds.) Routledge, 2013. The Role of Governance in Asia, (ed.) Institute of Southeast Asian Studies, 2004. 他
第24回受賞作品(2020年度)
谷口 美代子 著
『平和構築を支援する -ミンダナオ紛争と和平への道』
(名古屋大学出版会 2020年)
| 選評(早稲田大学理工学術院教授 北野 尚宏) | |
本書は、フィリピンのミンダナオ紛争を、国家、イスラーム系反政府武装勢力に、地元ムスリム有力氏族(クラン)を加えた三者間の相互関係として捉え、歴史的視点で分析した力作である。ミンダナオ紛争は、その和平プロセスに日本が深く関与し、人びとが尊厳をもって安心・安全に暮らせる社会を目指す「人間の安全保障」の考え方が現場レベルで実践されてきた、平和構築の代表事例のひとつといえる。しかし、長期化し複雑化した紛争の全貌を把握した上で、適切な外部支援を行うことは容易ではない。筆者は、ミンダナオ島南西部で平和構築関連の事業に従事する中で、様々な疑問にぶつかり、「この地域における問題を歴史的視点からより深く理解し、人びとにとってより効果的な協力を行うための一助になれば」と思い立ち、学術研究を開始する。本書は、膨大な文献レビューをもとに、前イスラーム期にまで遡り、ミンダナオの社会構造や統治制度とその実情の変遷を明らかにするとともに、反政府武装勢力の生起・発展や、その後の和平プロセスと平和構築の取組みを丹念にたどっている。中でも筆者は、国家、クラン、反政府武装勢力の競合・協調関係に焦点を当て、国家が統治のために有力クランとの利害関係を深め、クラン間抗争と暴力を助長する一方で、一部のクランは反政府武装勢力の母体となっているという複雑な実相を明らかにしている。ミンダナオ紛争をめぐる和平プロセスは、2018年にバンサモロ基本法が成立し、2019年にはバンサモロ自治地域・暫定自治政府が設立されるという大きな転機を迎えた。筆者は、町レベルでの平和構築の実践成功事例の分析結果も踏まえて、2022年のバンサモロ地域政府設立に向けた課題として、多民族を包摂する公共空間の創出や平和の文化を定着させることの重要性を指摘している。本書は、ミンダナオ紛争を理解する一助となると共に、他の地域の紛争を理解する上でも有益な視点や示唆を提供している。時宜を得た出版であり、大来賞にふさわしい作品である。筆者が、今後、実践と研究を融合させ、更なる飛躍を遂げられることを期待したい。 |
 |
著者略歴
谷口 美代子 (たにぐち みよこ)
広島県出身。東京大学大学院総合文化研究所博士課程修了。博士(国際貢献)。現在、(独)国際協力機構、国際協力専門員(平和構築)。1990年代後半より、国連機関、JICA、NGOなどを通じて開発協力(平和構築)に従事。長年、開発実務を通して得た知見を学術研究として体系的な知に転換し、実践と研究の両者を架橋することで新たな知識形成を図ることに注力。アジア太平洋研究賞(井植記念賞)、第32回アジア・太平洋賞特別賞、国際開発学会奨励賞を受賞。
主要著書
“Rethinking ‘Liberal Peacebuilding’: Conflict, Violence, and Peace in Mindanao.” Social Transformations: Journal of the Global South, 7 (1) 2020、“JICA’s Assistance for the forcibly Displaced in Conflict-Affected Countries in Middle East,” (eds) Dunar, Merthan, Exchange of Experiences for the Future: Japanese and Turkish Humanitarian Aid & Support Activities in Conflict Zone, Ankara University Asia-Pacific Research Center, (2018)、“From Rebels to Rulers: The Challenges of the Bangsamoro Government in Mindanao.” The Diplomat (2020) など。
第23回受賞作品(2019年度)
友松 夕香 著
『サバンナのジェンダー -西アフリカ農村経済の民族誌 』
(明石書店 2019年)
| 選評(法政大学名誉教授 絵所 秀紀) | |
本書はガーナ共和国北部の西ダゴンバ地域を対象にしたフィールドワークの成果である。総計22ヵ月に及ぶ現地調査に12年間にわたる思索を重ねた、著者渾身の作品である。「民族誌的手法は、実態の複雑さを描くだけではなく、政策の前提となっている定説を覆す新たな仮説や見解を現場から導き出すことができる」という言説を、見事なまでに実践した作品である。アフリカの農村女性をめぐる「定説」とは、「女性の周縁化」論(ボズラップ)、「女性の従属」論(フェミニスト人類学)、「資源配分の男女格差」論(バーゲニング・モデル)等に代表される議論であるが、これら既存研究には男性と女性の多面的で複雑な両義的関係性をとらえる「総合的な視野」が欠けていると著者は批判している。 本書は3部構成である。第1部では、ダゴンバ地域では1980年代から徐々に女性が自分の畑をもち耕作をはじめるようになったことの背景や要因が歴史的な観点から考察されている。人口の増加が土地利用の変化、主食用作物の変化、そして男性を中心として出来上がってきた耕作技術の陳腐化をもたらしたこと、他方で女性が担う家事仕事の効率化やトラクター賃耕が普及したことが指摘されている。第2部では、農村部の暮らしにおける資源配分の在り方とその経緯が考察されている。第3部では、1980年代以降に顕在化した、労働と作物をめぐる社会関係の蜜な発展が考察されている。耕作者が収穫を手伝った者へ収穫物の一部を分け与える慣行(サヒブ)の多様性が、ジェンダーの観点から描き出されている。こうした「厚い記述」を通して筆者は、女性たちが従来の仕事に加えて耕作という男性の仕事を「上乗せ」することになり、女性の負担が増す方向で男性と女性の生計関係が展開してきたと結論している。そして、「女性たちの人生における選択の幅」を広げるためには、「女性を支援する政策として、男性の耕作を支援する(男性たちの穀物の生産性を高める)」ことが必要だ、という刮目すべき政策提言を行っている。 きわめて質の高いフィールドワークによって支えられた、開発援助政策の再考を促すほどの説得力を持った、大来賞受賞にふさわしい作品である。本書のようなすぐれた作品が世に出たことを心から喜びたい。 |
 |
著者略歴
友松 夕香 (ともまつ ゆか)
大分県出身。2001年、カリフォルニア大学バークレー校政治学部を卒業。2003年から2005年、西アフリカのブルキナファソの環境・生活省で村落開発普及員として青年海外協力隊活動。2007年、国際農業研究協議グループ(CGIAR)・国際アグロフォレストリー研究センター(ICRAF)ナイロビ本部にて訪問研究(農林水産省/国際農林水産業研究センター(JIRCAS)による平成18年度国際共同研究人材育成推進事業)。
博士論文の調査地のガーナ北部で、農村部の女性たちの日々の労働の現実を目の当たりにする。以来、女性の経済的な自立と地位の向上を目標に、女性の農業を推進してきた国際開発政策に批判的関心をもつようになる。2015年、東京大学大学院農学生命科学研究科で博士号を取得。東京大学東洋文化研究所(日本学術振興会特別研究員RPD)、プリンストン大学歴史学部(ポスドクフェロー/訪問研究員)を経て、現在は京都大学人文科学研究所(日本学術振興会特別研究員PD)でジェンダーと農業、環境をテーマに開発政策の歴史的研究を進めている。
第22回受賞作品(2018年度)
堀江 未央 著
『娘たちのいない村 -ヨメ不足の連鎖をめぐる雲南ラフの民族誌』
(京都大学学術出版会 2018年)
| 選評(国連UNHCR協会理事長、東洋英和女学院大学院客員教授 滝澤 三郎) | |
中国では、一人っ子政策の結果として男児が相対的に増え、跡継ぎとなる男児を望む漢族の農村では深刻な嫁不足が起きている。漢族と少数民族の経済格差も大きい。これを背景に西南の少数民族地域から華東・中南農村地域への女性の婚姻移動が見られ、「娘たちのいない村」が増えている。 本書は、中国雲南省の少数民族のラフ村落からの女性の婚姻移動の動態を、彼女達を送り出す社会における家族やジェンダー観の変化、女性の位置づけと婚姻のあり方の変化、すなわち「送り出し社会の論理」に着目して解明している。移動を生み出す要素を探ると同時に、出身村落での女性達の夢と迷い、葛藤と逡巡、時には自ら望んで、ときには騙されつつ村を出る決断をする未婚の娘や若い妻達の心の動きが描き出されている。 本書は、ミクロなレベルの文化人類学的研究であるが、一人っ子政策や対外経済開放といった国家レベルの政策が辺境の村に及ぼす社会的影響を感じさせる研究でもある。中国国内でのラフ族の村から漢族の村へ、そこから都市への女性の移動が、ミャンマーのラフ族の中国ラフ族の村への女性の国際的な移動連鎖を引き起こしているとの指摘も興味深い。 外国人によるフィールドワークが困難な中国において、辺境に単身で2年半住み込み村の人々の信頼を得ながら調査をやり抜いた粘り強さと好奇心は賞賛に値する。方法論的にも、エスノエージェンシー理論という手法を用いて、少数民族の女性の移動に伴う婚姻や人格観念の流動性や多重性を描き、オリジナリティーの高い人類学的研究となっている。ほかの地域における同種の研究や、ほかのタイプの越境移動、例えば難民研究にも適用できるだろう。 文章は読みやすく、興味深い写真も多く、人類学だけでなく開発問題や人の移動問題に関心のある研究者や学生に勧めたい。新進気鋭の著者が、大来賞受賞を機に更なる飛躍をとげることを期待したい。 |
 |
著者略歴
堀江 未央(ほりえ みお)
1983年大阪府生まれ。2015年、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程修了、博士(地域研究)。京都大学東南アジア研究所連携研究員を経て、現在、名古屋大学高等研究院特任助教。
主な著作に、「中国雲南省ラフ族女性の遠隔地婚出-ラフ社会における結婚との関わりに着目して-」『東南アジア研究』52巻1号(2014年)、「ヨメ不足の連鎖がもたらす女性の移動と越境―中国・ミャンマー国境域におけるラフ女性の事例から―」『旅の文化研究所研究報告』No. 26(2016年)、「[研究動向]女性の越境移動研究の展開―アジアにおける婚姻移動を中心に―」『社会人類学年報』第43号、145-163頁(2017年)など。
第21回受賞作品(2017年度)
田中 由美子 著
|
|
| 選評(政策研究大学院大学 教授 大野 泉) | |
本書は、タンザニア農村の土地所有制度に着目し、農村女性の土地にかかわる諸権利について丹念な実証的調査を行い、ジェンダーの視点から開発政策・事業への示唆を考察した労作である。 著者の田中由美子氏は、国際協力機構(JICA)でジェンダー専門家の草分けとして長年第一線で活躍してきた。それゆえ、フィールドで培った知見にもとづき、世界銀行などで広く受容されている「女性が土地を所有すればエンパワーされ、経済的自立につながる」という土地権の近代化論に対して疑問をもち、仮説を立て、ケーススタディを通じて検証を試みるという、意欲的な研究が生まれたのだろう。 本書の優れている点として、3つあげたい。第1に、キリマンジャロ州ローアモシ灌漑地区を対象に1845人の土地所有者のデータを収集し、農村女性による土地の自己名義登録や、(営農権・収益権・処分権利を含む)土地の管理権の経時的変化をたどるなど、詳細な調査を行っていること。(なお、ローアモシ灌漑地区は、1980年代に円借款で稲作圃場や畑地圃場を造成し、その後もJICA専門家によるイネの栽培技術指導や無償資金協力による精米所建設を行うなど、タンザニアにおいて日本が長年、農村近代化を支援してきた地域でもある。) 第2に、農村女性たちが「価値あると思うこと」に焦点をあてた聞き取り調査を行い、既存のジェンダー平等論を超えて、質的に深みある聞き取り調査をしていること。第3に、比較分析の視点を交え、土地権の近代化論をふまえたアプローチを採用したケニア・ウガンダ・ジンバブエや、大規模灌漑事業を通じたスリランカの土地配分の結果と対比しながら、タンザニアのケーススタディの位置づけを明確にしていること、である。 本書はオーソドックスな研究手法を採用しているが、JICA事業で培ったネットワークを活かした土地権データの収集・分析や、現場感覚ある提言が散りばめられており、学術性と実践の両方を兼ねそなえた魅力的な研究になっている。また導入部分に、開発理論の変遷とジェンダー平等論を関連づけた概観があり、初心者にとっても分かりやすい内容になっている。土地を所有することに対する価値観が男女でどう違うか。本書が問いかけた視点は、タンザニアだけでなく、日本においても検証に値するのではないだろうか。 |
 |
|
著者略歴 |
|
佐藤 仁 著
|
|
| 選評(法政大学教授 絵所 秀紀) | |
読者に「開発研究の面白さ」を伝えたいというのが本書の目的であり、そもそも「開発研究」という領域が「学問として成り立つのか」という問いかけに答えたいというのが筆者の思いである。本書は「第Ⅰ部 開発・援助の知的技術」、「第Ⅱ部 開発・援助の想定外」、そして「第Ⅲ部 開発・援助と日本の生い立ち」の3部から成り立っており、さまざまなテーマを取り上げながら、開発の意味や技法、そして開発研究という学問のあり方について縦横無尽に論じたエッセー集である。 本書の魅力は、なんといっても「開発研究」というテーマも方法も確立していない領域に果敢に取り組んだ点にある。「開発研究」の特徴は、開発にかかわる「さまざまな問題の発見」と「課題の解決」を求める点に特徴がある。「問題」が先で「方法」が後という学問領域であるため、既成のディシプリンを機械的に応用するのではなく、問題の発見と同時に分析方法自身をも模索せざるをえない。なんともやっかいな研究分野である。本書の第Ⅰ部と第Ⅱ部で、筆者はアマルティア・セン、アルバート・ハーシュマン、ジェームズ・スコットといった「越境人」の議論から得られたインスピレーションを批判的かつ精力的に吸収し、生活の質の評価、事例分析の意義、分業のもたらすリスク、「想定外」による開発の失敗、被災者へ援助物資の分配方法、「資源の呪い」の克服手段といったさまざまなテーマを取り上げている。どの章からも、従来見過ごされてきた開発にかかわる重要な論点が浮かび上がってきており、見事である。 第Ⅲ部でとりあげたテーマは、Ⅰ部およびⅡ部とは関連はなく、我が国の援助史・援助体制をとりあげたものである。1950年代に着目し、「賠償に先立つ経済協力」あるいは「復興を中心に見据えた経済協力」という理念の系譜をえぐり出した点は、歴史研究としても見るべきものがある。 本書は開発研究の一つのすぐれた出発点として高く評価できる。筆者には、今後さらに分析概念に磨きをかけてわが国の開発研究を新たな高みへと飛躍させてくれることを期待したい。 |
 |
|
著者略歴 |
|
| 一覧表に戻る |
|
第20回受賞作品(2016年度)
宮城 大蔵 編著
|
|
| 選評(政策研究大学院大学 教授 大野 泉) | |
本書は、日本が戦後70年余にわたりアジアとどのような関係を構築してきたかを多面的に綴った本格的な通史である。編者である宮城氏を含む7名の執筆者は、アジア外交史の第一線の研究者であり、それぞれの専門分野の最新の学術成果を反映した魅力的な書物に仕上がっている。単著ではないが、編者が描いた構図のもとで、時代ごとの史実が全体として一貫性をもって提示されている。 21世紀の今日、「アジアの活力を取り込む」ことが日本の成長戦略の要諦になっている。今や、「アジアの中の日本」は自明とされる。しかし、本書を通じて戦前の歩みや、戦後から現在にいたる史実を学べば、同地域の国々と日本の関係は単線的でなく紆余曲折があったこと、日本にとって「アジア」という言葉自体が、範囲も力点も時代によって「伸縮自在」で可変的なものであったことが分かる。 第二次世界大戦で日本はアジアに侵攻した。戦後日本は、賠償交渉や経済協力を通じてアジア各国との関係の正常化に、実に大きなエネルギーと外交努力を払ってきた。当然ながら、「負の遺産」をもつ日本に対する、アジア各国の反応はさまざまであった。その後、日本は驚異的な復興・発展を遂げ、アジアで最初の先進国、経済大国になった。そして今、かつての「停滞のアジア」は「繁栄のアジア」へ変貌をとげ、韓国・中国等の新興国の台頭は著しく、日本の経済面での相対的地位は低下しつつある。 本書の重要な伏線は、戦後日本がアジアと関係構築を図るうえで政府開発援助(ODA)を含む官民の経済協力が果たした役割を分析し、散りばめていることだ。戦後賠償、福田ドクトリン(1977年)、日中平和友好条約の締結と対中円借款供与の開始(1979年)、プラザ合意(1985年)やアジア通貨危機(1997年)後の裾野産業育成・産業高度化支援など、日本は常に「対米協力」と「自主外交」のバランスをとりながら、インフラ開発・人材育成・産業協力など、経済面を中心に、アジア地域秩序の構築を担ってきた。 新しい時代に入り、日本は今後、アジアとどのような関係を構築していくのか、アジアでどのように官民協力を展開していけばよいか。本書はこうした問いかけへの、貴重な知的基盤を提供している。その意味で、開発協力・経済協力に取り組む官民の実務者やビジネスマンにとって必読書といえよう。 |
 |
|
編著者略歴 宮城 大蔵(みやぎ たいぞう)1968 年東京都生まれ。立教大学法学部卒業後、NHK記者を経て一橋大学大学院法学研究科博士課程修了。博士(法学)。北海道大学大学院法学研究科専任講師、政策研究大学院大学助教授等を経て、上智大学大学院グローバルスタディーズ研究科教授。 |
|
|
|
|
19回受賞作品(2015年度)
古川 光明 著
|
|
| 選評(東洋英和女学院大学大学院 教授、国連難民高等弁務官事務所 元駐日代表 滝澤 三郎) |  |
| 国際開発研究大来賞の目的は、国際開発の様々な課題に関する優れた指針を提供する優れた研究図書を顕彰することにある。受賞作品は「貧困削減レジーム」の援助行政メカニズムをアカデミックに鋭く明快に解明して、新たな方向性を示したものであり、まさにその目的にかなうものである。 本書は開発援助の実務者による学術研究書であるが、その学術的価値は、明確な問い、社会科学的な方法論と実践可能な結論の提示にある。まず、「貧困削減レジーム」の見直しが進むのは貧困削減レジーム自体に欠陥があるのか、それともレジームが徹底されていないためなのかという問題意識が明確である。 研究方法においても独自性が際立つ。貧困削減レジームのきっかけとなったいわゆる「プロジェクトの氾濫」は経済成長や貧困削減にどのような影響を与えたか、一般財政支援GBSの成果は実際にはどうであったか、などについて、乳児死亡率と初等教育修了率、経済成長率などを使いつつ定性的・定量的に分析している。ドナーと途上国政府の関係の変容過程、「援助の政治」と「実施の政治」の乖離など、「貧困削減レジーム」の実態を解明してゆく方法は見事であり、印象的な図表の使用も説得力を増している。実践面での応用性であるが、著者の問題意識がJICAタンザニア事務所の実務の中で生まれたこと、ドナーと途上国政府の関係者の意識と行動を熟知していることもあって、本書の提示する結論と今後への示唆は現実的である。中国など新興ドナーや民間企業との連携の必要性の指摘もうなずける。 本書は国際水準を満たす本格的学術研究書であり、日本だけでなく外国の開発援助の研究者・実務者にも広く読まれるべき作品である。選考委員会でも満場一致で決まった今回の受賞を、開発研究の将来にとっても明るいニュースとして祝いたい。 |
|
|
著者略歴 |
|
|
|
|
第18回受賞作品(2014年度)
栁澤 悠 著
|
|
| 選評(法政大学教授 絵所 秀紀) | |
| 中国と並んでこれからの世界経済をリードすると期待されているインド経済の成長の軌跡を、イギリス植民地期の19世紀末にまで遡って描き出すという、まことに気宇壮大で骨太な研究書である。本書は、独立前と後との経済の連続と断絶を描き出した、我が国では初めての著作である。長年にわたるフィールドワークと膨大な文献探索によって裏打ちされている。著者の主張は序章で10点にわたって整理されているが、とりわけ強調されている点は、「歴史的な変化の累積の帰結」として現代インドの経済と社会を理解するという歴史的アプローチの重要性であり、インド経済の全体像は「農村社会の二層性」によって規制されるという「構造的な特徴」をもっていることの指摘である。「農村社会の二層性」とは「農村の下層」と「農村の上層」の二層性を指す。著者は、19世紀末から始まった「農村社会の下層階層の上層階層への抵抗や自立化の動きを通して実現された、ハイアラーキー関係の弱化」によって「農村市場が拡大」し、ついには現在の高度経済成長を市場面から支えるまでになった、と説明している。インド経済の発展経路の特徴を「下からの発展」、「農村需要が果たした中心的な役割」、「19世紀末以来の農民階層による農業生産性上昇を目指した経験によって支えられた、独立以降の農業生産の発展(緑の革命)」、そして「独立以降の国家主導の輸入代替工業化」に求めたものである。「下からの発展」という農村下層民の自立化への主体的営為を重視する著者のアプローチを現代インド経済にまで拡張し、縦横無尽に議論を展開した渾身の著作である。 選考委員の間からは、本書で著者が示した経済発展の経路は発展の糸口が見えない発展途上国にとって一つの明るい指針を示す、学問の醍醐味を感じることのできる著作、インド市場の特徴を分析した貴重な研究、等々といった高い評価を得たことも付け加えておきたい。 |
 |
|
著者略歴 |
|
第17回受賞作品(2013年度)
森 壮也・山形 辰史 著
|
|
| 選評(法政大学教授 絵所 秀紀) | |
| 本書は、「障害と開発」という問題に鋭く切り込んだ著作である。「開発学」と「障害学」という2つの領域を、「障害の社会モデル」という観点から統合的にとらえた先駆的な研究成果である。筆者たちは、障害者は「不利を被りがちな人々」の間でも、より一層不利を被りがちであることに着目し、その原因を障害の多様性と少数である点に求め、それが国際開発のテーマとして取り上げられなかった理由であると論じている。そして障害の医療・社会福祉の観点に立った個人・医療モデルを批判し、障害の社会モデルこそ有効なアプロ-チであると主張している。障害データの国際比較を批判的に紹介した第2章、および障害者のミクロ生計分析のサーベイをとりあつかった第3章は見事なもので、「障害と開発」分野の既存データおよび研究の全体像を知る上で格好の入門である。本書の後半は、フィリピンのマニラ首都圏とバタンガス州ロザリオ市でのフィールド調査に基づいた実証分析を行った成果である。調査対象は、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害をもつ障害者である。第5章と第6章は、それぞれ障害者の所得の決定因と障害者政策の効果を計量分析の結果である。教育と所得とが相互に高めあう関係になっていること、女性障害者の所得は男性障害者の所得と比較して著しく低いこと、障害者得点制度の浸透度が低いこと、障害者当事者団体に所属していれば特典の利用頻度が高くなることが結果として得られている。手堅い実証分析で、「障害と開発」という分野では先駆的な成果である。 本書は、アマルティア・センが提唱したケイバビリティ・アプローチを具体化し、従来の貧困研究で脱落していた領域に光をあてた画期的な研究成果である。本研究成果は、英文でも出版される予定とのことであり、世界への発信を期待したい。 |
 |
|
著者略歴 |
|
山尾 大 著
|
|
| 選評(政策研究大学院大学教授 大野 泉) | |
| 世界を揺るがしたイラク戦争から10年。本書は、その後、米国主導で進められたイラク再建プロセスに焦点をあて、膨大な一次資料を収集・分析し、今なお続くイラク政治の混迷の原因を考察した研究である。イラク社会で実際に何がおこったかを民主化、政党連合結成、選挙、治安回復等の切り口で克明に分析した優れた地域研究であると同時に、ガバナンス論もふまえ、近年の通説にチャレンジしている点が本書の魅力を高めている。 戦後イラクでは外部アクター(米国)により導入された民主化・地方分権化の制度が、内部アクター(宗派、部族等)のポリティクスと複雑に絡まり、社会固有の事情により形骸化していった。著者は、これこそがイラク再建が遅れた原因とみる。そして、国家機構の確立前に民主化や地方分権化を進めることの問題を提起し、ワシントン・コンセンサスの政治版ともいえるビッグバン改革に警鐘を鳴らしている。 冷戦後の内戦や地域紛争の頻発、今日の中東・北アフリカの民主化をめぐる混迷―こうした現実下において、平和構築や脆弱国家への支援は、21世紀の国際開発の重要な柱である。国家建設が外部アクターと内部アクターとの関係性のもとで進んでいくことが不可避な以上、外部から移植された制度と内部論理の各国固有の相互作用に注目した、本書の分析視角は、開発支援の実務者にとっても重い意味をもつ。 イラク再建は道半ばであり、ネーション・ビルディング過程の理論化という点では、まだ完成途上の研究と言えようが、21世紀の国際開発の重要課題に対し、日本の研究者が現時点でこうした形で問題提起をすること自体、意義あると考えた。山尾大氏には、将来を担う地域研究者として、ぜひともイラクの国家再建に寄り添って研究を続け、ネーション・ビルディングと国民統合、外部者が果すべき役割を洞察する第二弾を世に出してほしい。こうした願いもこめて本書を選考した。 |
 |
|
著者略歴 |
|
第16回受賞作品(2012年度)
佐藤 百合 著
|
||
| 選評(政策研究大学院大学 教授 大野泉) | ||
| 本書は、長年にわたり現地と日本を行き来し、インドネシアを見つめてきた研究者が、新しい発展段階にきたインドネシアの「今」を伝え、同国の将来、ひいては日尼関係を展望した、気迫に満ちた著作である。特に中国、インドに次ぐ第三の新興経済大国という枠組み設定でインドネシアの将来を探っている点がきわめて新鮮である。 アジア金融危機を引き金としたスハルト体制の崩壊、急進的な地方分権化による政治不安定、地震・津波、鳥インフルエンザなど、インドネシアは過去10年余、「混乱と停滞」に見舞われた。金融危機直後に、腕組みしたIMFのカムドシュ専務理事(当時)の前で支援プログラムに署名するスハルト前大統領の写真は今なお記憶に新しく、複雑な思いで受けとめた人は多いのではないだろうか。しかし、その後、インドネシアは大きな飛躍をとげている。2004年のユドヨノ政権成立後、政治的安定を取り戻し、リーマンショックをへた2009年以降は、中国とインドに続くアジア第三の新興経済大国として頭角を現しつつある。開発援助関係者はややもすると、インドネシアを主要な援助供与先としてとらえがちだが、G20のメンバー国、資源国、民主主義が定着したイスラム教国として、今や同国は経済面のみならず、ソフトパワーにおいても存在感を増しているのだ。 著者は詳細なデータ分析や文献調査をもとに「人口ボーナス」と「政治的安定」の二つの条件から、インドネシアは今後も持続的経済成長を遂げる可能性が高いと論じ、日本はこうした「アジアの経済大国」インドネシアと新しい関係を築くべきと主張している。スハルト時代からの大転換、経済テクノクラートや産業人を概観した幾つかの章は、長くインドネシアに寄り添い、政治家・行政官から研究者、企業家、市民に至る様々な人々と信頼関係を築き、同国を多角的に見つめてきた著者だからこそ書ける内容で、本書の分析に厚みを与えている。 大来賞は今年から実践面を重視することになったが、本書は学術性をそなえつつ、ビジネスマンや開発援助関係者を含む多くの読者の関心に応えるタイムリーな良書である。新興国への道を歩むインドネシアの「今」を政治・経済の両方の視点から、しかも歴史観をもって記した著作という点で決定版である。 |
 |
|
|
著者略歴 主要著書:
|
||
第15回受賞作品(平成23年度)
| 該当作なし | |
第14回受賞作品(平成22年度)
田辺 明生 著
|
|
| 選評(政策研究大学院大学 名誉教授 大来 洋一) | |
| 本書は、カースト制度について論じているが、カーストがヒエラルヒーであり、権力による支配の構造であるという通常の理解に対して、カーストがそのようなものであるのは、政治・経済の側面での話であり、そのような構図の影に隠れた日常生活のレベル、とくに祭祀など宗教的、精神的次元では「存在の平等性」という原理が働いている、と指摘する。それは、すべての存在(人間)の根源的な平等性と、現実の世界でのカーストにもとづく支配や差別との間にある矛盾を「媒介」する原理であり、それは植民地時代の以前から、祭の場などで観察できるものとして存在してきた。インド社会における民衆の政治参加は、地域社会の中の派閥を通じる国家資源の獲得競争(賄賂や横領)という否定的な側面を含むが、それを乗り越える社会協力のための「文化的資源」として、この「存在の平等性」に期待できるという。1990年代の民衆主導の反差別、反カーストの動きにもそれは窺われる。このような本書の主張は、楽観的かもしれないが、一つの見方であろう。
著者は、カースト制度の変遷をインドのオリッサ地方で追いながら、同時に地域社会や日常生活の中での「存在の平等性」という原理の生き残りを確かめていく。この作業は大変な労力を伴うものであったと思われる。多くの聞き取り調査、フィールド調査、貝葉文書の収集、祭祀における儀礼、とくに生贄のお供えの克明な観察など、長期の実地調査が行われている。また、膨大な文献の読み込みが行われている。審査会は、これまでも地道な現場での研究を評価してきており、今回も同様な観点から本書を推す声が多かった。なお、カースト制度に平等性をもたらす側面があるという歴史学の中の一派との違いが不明である、という指摘もあったが、インドに昔から「存在の平等」という観念があったことを気づかせてくれることを評価するという意見もあり、全体として本書を選ぶことで意見の一致をみた。 本書は、A.Senや、Rawlsなどの議論も吸収しており、開発経済学にもつながる業績であると思われる。ただ、審査員の多くが経済学の畑の者であったために、本書の内容を十分に理解するのは容易ではなかった。もし、本書が簡潔で平易な文体で書かれていたら、他の候補作を大きく引き離す評価を得ていたと思う。他の候補作では、高橋基樹氏の『開発と国家:アフリカ政治経済論序説』を力作として推す声も多かったが、力が入るあまり、議論の展開が若干性急になった部分があったのは惜しまれる。また、平野克己氏の『アフリカ問題:開発と援助の世界史』を推す声もあったが、氏の既受賞作との重複感があることから見送られた。 |
 |
|
著者略歴 主要著書: |
|
第13回受賞作品(平成21年度)
武内 進一 著
|
|
| 選評(株式会社国際開発ジャーナル 代表取締役 荒木 光弥) | |
| 本書は現代アフリカ紛争の根源を探求した著者・武内進一氏の集大成ではないかと思う。筆者は対アフリカ援助がクローズ・アップされた時、混迷のアフリカ社会の歴史的な実像を勉強しようと手にしたのが「現代アフリカの紛争-歴史と主体」(武内進一編、アジア経済研究所)であった。また、紛争予防外交を調べた時には「アフリカの国内紛争と予防外交」(NIRA・横山洋三共編、国際書院)を参考にした。この時も武内氏は第4章予防外交の新たな展開で第2節と第3節を執筆している。その他、多くのアフリカ研究会でもルワンダをベースに紛争の根元をみつめた報告を行っている。今回は、これまでの研究をベースに一つの研究の型にまとめあげたと言えそうだ。 たとえば、本書はアフリカにおける紛争は主体が国家の軍隊ではなく民兵など小さな単位になっているため、被害は市民に集中するといった既存の理論があるが、それら理論とルワンダの事例を組み合わせながら、さらになぜそのような状況が生じているのかを絶妙に描いている。既存の理論はアフリカの社会を単純化して描きがちであったが、本書においてはアフリカ社会の複雑さをより詳細に明確化している。そして既存の理論について、当たり前と思われていた点について、一つ一つあらためて考察し直している。それにより、新たな視点をいくつも呈示しており、通説をそのまま鵜呑みにするのではなく、極めて多様な視点を持って、アフリカを捉える必要性を感じさせてくれる。 さまざまな理論が活用されていることもさることながら、特に、ルワンダに関する極めて詳細で具体的な情報には驚かされた。巻末にはインタビューの資料や調査の際の写真が掲載されており、実践的な応用にも期待でき、本書で提示されている情報そのものの価値も高いであろう。さらに強調すべきは、随所に図を活用しながら、それぞれが非常にわかりやすく解説されている。また、本書は400ページを越える大作であるが、歴史や社会構造を説明する上でも、残された文献や人々の声を引用しながら描かれ、ページ数を感じさせないほど、読み物としても非常に魅力的なものになっている。 本書以外、戸堂康之氏の「技術伝播と経済成長」、本台進氏・新谷正彦氏共著の「教育と所得格差-インドネシアにおける貧困削減に向けて-」も大変高く評価でき、最終的な受賞作品を選ぶ際、至難であった。しかし本書は、今後の平和構築に向け大いに活用できる本として普及が進む可能性が高く、またその願いを込めて、受賞への推薦を後押しした。 |
 |
|
著者略歴 主要著書: |
|
第12回受賞作品(平成20年度)
牧田 りえ 著
|
|
| 選評(廣野 良吉 成蹊大学名誉教授) | |
| 本書は、バングラデッシュの農村における土地無し農民に焦点を当てた実態調査に基づいた研究である。周知のように、従来から多くの低所得国、最貧国では、土地無しに農民=貧困層の削減に取り組んでおり、その削減戦略としては、マクロ経済成長、人口増の抑制、農地改革、工業化による農村人口の都市への移動、農業生産における規模の拡大、農産物の多様化による生産性の向上が有効であると言われてきた。しかし、これらの戦略も、政治的・経済的・社会的・生態的制約条件に直面して、成果が期待ほどでていないのが現状である。バングラデッシュもこの例外ではなく、相変わらず南アジア地域でも最高の失業率や貧困率を未解決のままできている。 本書の特徴は、総合農村開発研究所(IIRD)というNGOが指導する「パートナシップ企業」による非耕作部門での所得創出事業が、一農村地域における貧困削減効果をいかにもたらしているかを綿密な実態調査に基づいて実証している点にある。本書は、現存する多くの制約条件の下で、単なる政府補助金対策や、政治的構造改革による社会的軋轢・混乱をもたらすことなく、グラミン銀行と同様に、途上国が推進できるもう一つの貧困脱却の道があることを示している。NGOという政府以外の市場プレーヤーによる市場原理に基づいた、経済活動の効率化を通じた支援活動というアプローチは、そのもろもろの限界にも拘らず、財政赤字に直面している多くの途上国の政策担当者にとっても示唆に富み、大きな期待と希望を与えるものであるということができるであろう。特に、単純生産的生業から拡大生産的産業へ(from survival to accumulation)と発展するために農民自身が必要な技能・技術と農村を取り巻く資金、市場、法・行政等の諸条件整備がいかなるものかを明確にしている。実態調査の枠組みと方法が明確であり、フィールド調査が有効に活用されている点も高く評価したい。 しかし、学術的には、本書には厳密な統計分析がなく、経済理論的考察も不足している。さらに、実践面では、パートナーシップ企業という形で参入したNGO自身に相当の運営管理能力や技術的専門性等が求められるが、一般のNGOにはその能力・体制も不備であろうから、はたしてこのアプローチが、多くの途上国で普及できるかどうかも気になる。 しかし、日本人学者が日本人の眼で見た途上国の農村分析を英文で発表・出版し、日本の対外発信強化に資すると同時に、国際的な開発政策議論へ多数の日本人学者が参加することの大切さを常に強調、訴えてこられてきた大来先生の遺志に応えるという意味もあって、本書の推薦を最終的に合意したということを付記したい。 |
 |
|
著者略歴 主要著書: |
|
第11回受賞作品(平成19年度)
湖中 真哉 著
|
|
| 選評(廣野 良吉 成蹊大学名誉教授) | |
| 本書は、ケニアのサンブルにおける生業経済と市場経済の並存の様相を民俗誌的なアプローチによって分析した試みである。サンブルの牧畜農村で従来の生業経済が市場化に如何に対応してきたか綿密な実態調査を通じて明らかにし、両者の併存的複層化を牧畜二重経済原理として一般化しようとしている試みは評価できる。特に、調査の枠組みと方法が明確であり、フィールド調査が有効に活用されており、家畜商の取引の記録からの分析は真に興味深い。 経済の実態を数字だけから把握するのではなく、彼らの日常生活の言動を通して経済行為の背景にある文化的要素もふくめて鋭く分析している点に、文化人類学者ならではの視点が生きている。市場経済に組み込まれるか、あるいは生業経済を守り続けるかという二者択一的な発想ではなく、若干無理はあるが、家畜を地域通貨として位置づけ、その市場機能を評価・分析して、アフリカでは、市場は機能しないという「伝統的な考え方」に終止符をうとうとした意図に拍手を送りたい。さらに、「牧畜二重経済が消滅するという予測を前提にすることで、結果的に彼らの内発的発展の萌芽を摘み取ってはならない」という文化人類学者的視点は、開発問題の経済学的分析から開発政策を論ずる経済学者にとって一つの警鐘だと思う。そして、開発政策が地域住民の経済福祉に資するものであるためには地域・住民の価値観や行動を的確に把握する必要があるという指摘は、従来からなされていたが、本書はケニア牧畜民について真にそのような成果をあげているといえるであろう。 大半の途上国政府は伝統的な生業経済に市場経済原理を導入し、経済の効率化を通じて貧困削減目標を達成しようとしているので、本書は、開発政策担当者やその協力者に対して示唆に富む。 しかし、本書では家計簿からの調査はサンプルが二つのみであり、つっこんだ分析になっているとはいいがたい。また、科学的な数量分析ができていない点も気になる。さらに、先進市場経済でも、農家の自家消費は多いのが現実であり、これをもって二重経済の証左にはならないという指摘もある。この牧畜二重経済体制を「内発的発展」のモデルとしているが、政策担当者は、二重経済体制のメリットに対する関心と同時に、それを確立する際の条件整備(政策インセンティブを含めて)の難易度に関心がある。この点の分析の一般化が努力不足であったといわざるを得ない。 以上の論点からわかるように、審査委員の間でかなりの異論が最後まで飛び交ったが、若手の学者がユニークなデータを収集し、独自の分析の展開を通じて、開発議論への新しい挑戦を大切にするという「大来賞」の狙いから、本書の推薦を最終的に合意したということを付記したい。 |
 |
|
著者略歴 主要著書: |
|
第10回受賞作品(平成18年度)
谷 正和著
|
|
| 選評(荒木光弥 国際開発ジャーナル社) | |
| 本書は多くの人びとに砒素汚染の恐ろしさを知ってもらう啓発的な教科書であるとともに、砒素汚染を防止するための外国援助者にとっても「援助する意味」を考えるうえで参考になる実践の書だといえる。 著者の谷正和助教授(九州大学大学院)は94年に発足したNGOアジア砒素ネットワークと行動を共にしながらバングラデシュ、ネパールの現場で人類学的調査を行い、本書ではバングラデシュのシャタム村とアルマ村に入り、人類学的な角度から村社会の仕組み、そこに住む伝統的な村人たちの深層心理に分析の目を向けながら得た新しい知的発見と援助する者への教訓を収めている。 本書の特色を挙げると、第1に、深刻な砒素中毒汚染をバングラデシュの二つの農村から訴え、貧しさゆえの問題の複雑さ、そして根深さを日本の多くの人びとに知ってもらおうという意図をもって筆をとっていること。審査では、文献レビューや論理性の不足が指摘されたが、著者が最初から学術的探求でなく、学者の目で捉えた現実からの生きた情報を少し加工して一般大衆に“啓発の教科書”として発信しようという執筆意図を勘案して「大来賞」に値するものと判断した。 第2に、貧しい農村での砒素汚染を人類学、環境人類学というジャンルから捉えていることである。通常、砒素といえば薬学など医学部門が登場したり、農村開発といえば経済学や社会学などからのアプローチが主流を占めている。その意味で、本書の環境人類学というアプローチに新鮮さを感じる。冷徹な目で農村の歴史のなかに閉じ込められたような人間を鋭く観察する。そのうえで対応を考えようとする。 第3に、現場体験による人類学的な視点で村と人間分析を行い、改めて外国人が「援助する」という意味を問うていることである。これをODA開発調査からみると、他に類を見ない高品質の現地調査報告書ともいえる。 |
 |
| 著者略歴 谷 正和(たに・まさかず) 1957年生まれ。1991年アリゾナ大学大学院人類学研究科博士課程修了。アリゾナ大学応用人類学研究所研究員、宮崎国際大学比較文化学部助教授、九州芸術工科大学芸術工学部助教授を経て、2004年より九州大学大学院芸術工学研究院助教授。 主要著書: 『民族考古学序説』(共著、1998年、同成社) 『Anthropology of Consumer Behavior』(共著、1995年、Sage University Press) 『Kalinga Ethnoarchaeology』(共著、1994年、Smithsonian Institution Press) |
|
第9回受賞作品(平成17年度)
藤田幸一著
|
|
| 選評(大塚啓二郎 FASID連携大学院プログラムディレクター) | |
| 途上国の実態を知ろうとすれば、フィールド調査が不可欠である。しかしフィールド調査は誰にもできるほど生易しいものではない。大事なことは途上国の人々と話をしながら「Relevant」な質問を発することができるか否かである。「なぜこんなことが起こっているのか」、一見不可解な現象に遭遇したら、それを徹底的に追及していくことが調査の基本である。しかし不可解な現象を見つけるには経験が必要であり、データを駆使しながらその原因を解明するためには経済理論の知識や分析のセンスが必要である。本書は著者の経験と努力と能力が結実したまれにみる労作である。フィールド調査を志す研究者の一人として、本書の大来賞受賞を心からお祝い申し上げたい。 丹念な分析とともに、根拠のうすい通説を打破しながら新たな「正論」を打ち立ててくれているのが本書の魅力である。通説のように大農が小農を搾取しているわけではないし、井戸を所有している村の実力者が井戸に投資する資金的余裕のない貧農を搾取しているわけでもない。市場メカニズムが、競争を通じて搾取の発生を押さえ込んでいるのである。通説が主張するほどマイクロファイナンスが貧困削減の特効薬ではないことも示してくれている。著者ならではの研究成果が随所に織り込まれており、実に読み応えのある著作である。 当然のことながら、他の選考委員からの評価も非常に高いものであった。ただし、「分析がバングラデッシュに特有で、結論の一般性に疑問がある」という声があった。しかし、一般性のある発見をするためには丹念な実態研究を様々な場所で積み重ねる以外に方法はない。したがって、バングラデッシュに特化した研究を行ったことに問題はない。あえて勝手なことを言えば、受賞者にはバングラデッシュ以外の国おいても研究を重ねて欲しいとは思う。なぜならば、さらに一般性のある重大な事実をえぐり出してくれるに違いないと思うからである。 |
 |
| 著者略歴 藤田幸一(ふじた・こういち) 1959 年大阪生まれ。1982年東京大学農学部農業経済学科卒業、1986年同大学院農学系研究科農業経済学専攻修士課程修了、1992年同大学院農学系研究科 より博士(農学)を取得。農林水産省農業総合研究所研究員(1986年より)、東京大学農学部助教授(1995年より)を経て、1998年より京都大学東 南アジア研究所助教授。 主要著書: 『バングラデシュ農業発展論序説』農業総合研究所、研究叢書第114号、1993年 「制度の経済学と途上国の農業・農村開発」『農業経済研究』第74巻第2号、2002年 「農村の貧困と開発の課題」絵所秀紀・穂坂光彦・野上裕生編著『貧困と開発』日本評論社、2004年 『ミャンマー移行経済の変容』(編著)アジア経済研究所、2005年 |
|
第8回受賞作品(平成16年度)
石井菜穂子著
|
|
| 選評(浅沼信爾 一橋大学大学院教授) | |
| 本書は、長期経済発展の決定要因は何かという壮大な問題に、それは広義の「制度的な発展」であると答え、それを検証しようとした野心的な試みである。著者は、先進工業国の長期経済発展を歴史的に概観することによって、経済発展のための「環境条件」を、(1)技術革新力、(2)物的インフラ、(3)人的資本、(4)私的所有権、(5)社会的結合力、(6)ガバナンス、の6つであると想定して、長期経済成長率はこれら6要素からなる「制度のミニマム・セット」の発展度合いによって説明できると結論づけている。さらに、制度のミニマム・セットを「制度の6角形」で表し、制度の未発達がどの要素の欠如によるのかを明らかにして、長期的な経済成長促進の政策指針を提供している。 本書は、既存の標準理論を部分的に修正・拡張しそれを統計的に検証するといった手堅い研究ではない。長期経済発展は制度の発展が決定する、またさらに経済成長を促進する「環境条件」として6つの制度的要因があるという大胆な仮説から出発して、統計的な分析のみならず経済発展の歴史の検討、政策実務から会得した経験等々すべてを駆使して、読者に対する説得を試みている。著者の出発点である仮説と方法が大胆であるとするかあるいは無謀であるとするかによって、本書に対する評価は分かれる。経済発展と制度の間にあるいは制度の要素間に双方向的な因果関係があるとして、本書の学術的完成度を論難することは容易である。それにもかかわらず、著者が長期経済発展という壮大な問題に、理論、統計、歴史、政策実務経験のすべてを総動員して果敢に挑戦したその意欲は高く評価できる。この大来賞は、学術的な完成作品に対するというよりは、著者の意欲的な挑戦に対する選者の敬意の現れである。 |
 |
安原毅著
|
|
| 選評(廣野良吉 成蹊大学名誉教授) | |
| 本書は、メキシコ経済に内在する金融不安定性について論じた理論的・実証的研究である。本書の長所は、メキシコで実際に実施された自由化・開放化政策の実態に迫り、その効果のメカニズムを分析した点にある。本書に対する読者の最大の関心は、90年代を通じてメキシコの金融システムが大きく構造変化した結果金融システムが不安定化したという点にある。すなわち、新自由主義政策の下でのメキシコにおける国営企業の民営化、金融の自由化等が、IMFや世界銀行の期待に反して、マクロ経済の安定化政策との整合性を欠き、金融不安定性の増大と共に、諸々の経済的・社会的矛盾をもたらしている点である。著者はその根拠を、一方で金融仲介業務部門における「民営化の不始末」と他方では政府、通貨当局の誤った政策に求めているが、これは民営化・自由化政策の立案ないし実行において政治的圧力による非合理性や不徹底性や不透明性の排除が如何に重要であるかを物語っている。この意味で、メキシコの金融不安定性は、民営化・自由化政策そのものが根本的に誤りであるのではなく、その方法とマクロ経済政策との整合性にあるという著者の主張は、現在国・公営企業の民営化、金融の自由化、規制緩和を広く進めている多くの途上国の政策当局としても傾聴に値する。しかし、マクロ理論や文献サーベイの比重が高く、本書の表題とは異なって、メキシコの金融制度に主眼を置いた分析になっていないという点と、本書全体の展望や構成を説明し、統一的な分析フレームワークを提示する序章が無かったことが審査委員一同不満であったことを付言しておきたい。最後に、途上国の最大関心事であり、著者自身が意欲を示しているマイクロ金融の貧困削減への効果についての今後の理論的・実証的研究に期待したい。 |  |
第7回受賞作品(平成15年度)
平野克己著
|
|
| 選評(荒木光弥 国際開発ジャーナル社代表取締役) | |
| 審査員の一人は「図説か」といいながら読み込んでいくうちに本格的な学術書であることに気づいた。多くのグラフと表を駆使して、漠然としたアフリカ全体の経済論を鮮明にしていることを考えると、図説は単なる図説ではない。著者のチャレンジが感じられる。 折しも第3回東京アフリカ開発会議が開催され、アフリカの貧困問題が大きくクローズアップされていた。そうしたなかで、人びとは48カ国に及ぶ個々のアフリカ諸国の政治・経済問題ではなく、サハラ以南アフリカ全体を貫通する実像を知りたいと思った。アフリカを貧困にしている実像が知りたかった。その時、本書は貧困問題を大きく左右する経済に焦点をあてて、経済を通して多様なアフリカを理解する方法を教えてくれた。著者も「地域研究者としてアフリカの多彩な様相を追いかけながら、その多様さを理解するフレームとして積み上げてきた理解の様式を主に経済の側面に焦点をあてて、まとめて提示した」と述べている。 本論の核心は「成長しない経済」こそアフリカ問題であるとし、最終章で「成長しない経済」の行方を展望している。それによると、アフリカ総労働力の6割以上を吸収する農業部門の改革がまず行われなければ、国内市場も地域市場も深化せず、したがって工業化の可能性は開かれないとし、そのうえでアフリカの貧困問題はその貧困層の8割を構成するアフリカ小農の所得向上がない限り、決して貧困が削減されることはないと言い切る。 著者はそうした視点から日本が手がけたネリカ米の普及に熱心であり、草の根的な農村アプローチを主張する。アフリカ問題はグローバル・イシューとして重要であるにもかかわらず、日本での研究者は極めて少なく、欧米、アジア研究に比べて決して優遇されていない。そのなかで黙々と真摯に研究を続けてきた研究者への敬意が大来賞といえるだろう。 |
 |
第6回受賞作品(平成14年度)
石井正子著
|
|
| 選評(廣野良吉 成蹊大学名誉教授) | |
| 新しい研究視点を導入し、現場の開発・開発協力の事例・実態・要因分析から理論的体系化を試み、開発協力政策乃至実践で新しい有用な提言をする研究者の育成を刺激することにある。本書は、開発協力政策や実務で直接役立つ提言が見当たらないのが選考上最大の問題点であったが、開発研究に「語り」というインタービュー形式を導入して、現実を探ろうとする接近方法が新鮮であり、13ヶ月に及ぶムスリム社会での綿密な現地調査に基づく地道な研究が、地域研究者のみならず、途上国の経済・政治・社会問題の研究に関心ある総ての研究者にとっても手本となるということが評価された。フィリピンのムスリム社会については多くの文献が内外で出版されている中で、本書はムスリム女性に焦点を併せて彼女たちの社会的背景のみならず、その経済的・政治的・文化的活動を、彼女たちの日常生活実態の観察と彼女たちとの「語り」を通じて浮き彫りにしている。日本人一般が持つムスリム女性のステレオタイプ的理解・認識を排しており、実践面でもムスリム社会のジェンダー支援のあり方で若干示唆に富む点もある。しかし、ムスリム女性の行動様式についての理論的仮説がなく、ミンダナオ島の一地方での個人的観察に中心をおいているが故に、その結論が他の地域・社会への応用性があるのか、どの程度まで普遍性があるのかが検証されていないのが残念である。特に、戦後のフィリピンの経済発展で取り残されてきた他の地域社会の住民の行動様式との比較の中で、ミンダナオ島という一地方のムスリム女性の行動様式の特徴を分析してほしかったというのは、若年研究者に対しては余りにも過大な期待であろうか。最後に本書は一般的にフィリピンを含むアジアのイスラム社会の女性について関心と理解が薄い日本人にとっては、優れた紹介的書物であることを強調しておきたい。 |  |
脇村孝平著
|
|
| 選評(大塚啓二郎 FASID連携大学院プログラムディレクター/プロフェソリアル・フェロー) | |
| きわめて残念ながら、人類にとって最も根源的な悲劇である「飢餓」を、人類は地球上から撲滅することにいまだに成功していない。今年はアフリカの南部や東部で旱魃のために食糧不足が心配されている。つまり飢餓は、依然として人類にとって最も重要な今日的な問題の一つであり続けている。受賞対象となった本書は、英領インド時代の飢餓の実態をまさにそのタイトルにある通り、『飢饉・疫病・植民地統治』の三つの観点から鋭くえぐった名著である。著者によれば、インドで食糧生産が増大した1871年から1920年までの時期には飢饉・疫病が頻発し人口が減少したのに対して、その後の1950年までの時期には、農業生産は停滞したが飢饉・疫病は減少し人口は増大した。このパラドクシカルな現象はなぜ引き起こされたのか。著者は、学術的文献はもとより、点在する統計数値、膨大な植民地政府の報告書を総点検し、その謎にメスを入れていく。「なぜか」という問いを自ら発し、その答えを追い求める著者の研究姿勢は、実証研究の原点とは何かを教えてくれる。A.K.Senのエンパワーメントの議論を踏まえつつ、植民地政策の評価等、独自の視点を提示していることも高く評価したい。 1920年以降、センが問題にした1943年のベンガル飢饉までの期間になぜインドで疫病が減少していったのか、その教訓が描かれていないのは残念であったが、それは次の著作で解決してくれるものと期待したい。審査では本書に対して、「実践的活動へのインプリケイションが少ない」という批判もあったが、それはFASIDの関心がそこにあるからであって、国際的にも充分に通用する本書の学問的価値を否定するものではないと評者は理解している。 |
 |
第5回受賞作品(平成13年度)
黒崎卓著
|
|
| 選評 | |
| 経済開発論のミクロ的分析の国際的な主流は、いまやハウスホールド・モデルであるといっても過言ではない。このアプローチは、貧困問題の構造的側面を厳密に計量経済学的手法を用いて明らかにし、それに対する望ましい政策的対応を考えるうえで不可欠な分析トゥールになっている。こうしたアプローチを駆使しながら国際的に活躍をしている著者が、本来的に難解なこのモデルの本質をできるだけ分かりやすく解説しつつ、それを応用した実証研究の成果を集大成したことは、わが国の開発経済学の水準を高めるうえできわめて意義深い。類似の著書は英文を含めてほとんどなく、本書は、大学院生をはじめとして開発経済学を専攻する研究者の必読書であると位置付けることができよう。本書はハウスホールド・モデルだけを扱っているだけでなく、小作契約の有効性や農産物市場の効率性等の重要な問題についても、南アジアの事例を題材にしつつ、興味深い分析を展開している。深い経済理論の理解と、適切な実証的分析手法に立脚した本書は、国際水準に達した好著であることは疑いなく、それには高い評価が与えられてしかるべきであろう。ただし、開発経済学を学ぶうえでのハウスホールド・モデルの意義、それを応用することによって得られる政策的インプリケーションについて丁寧な説明が欠けていることが悔やまれる。果たしてどれだけの若手の研究者が、ハウスホールド・モデルを適用することに熱意を抱くようになったか、不安がないわけではない。 |  |
西川潤著
|
|
| 選評 | |
| 開発援助の初期のころは、経済成長の均霑(トリックル・ダウン)効果によって、その恩恵が自動的に民衆に広く裨益していくという考え方が開発援助の大宗を占めていた。それが次の段階では、経済発展の恩恵がいっこうに民衆に裨益していかない状況のなかで、依然として人間らしい生活を営められない貧困層が残されたままになり、開発援助はBHN(Basic Human Needs=人間としての基本的要請)を重視するようになった。現在、開発援助の主要テーマは「貧困削減」である。「人間開発指標」まで作成しているUNDP(国連開発計画)の人間開発報告書は、貧困は「人間の潜在能力」が開発されてないところに起因するというアマルティア・セン教授(ノーベル経済学賞受賞)の影響を大きく受けているが、今では人間中心の開発援助パラダイムとして台頭している。しかし、経済理論の領域では新古典派の段階にとどまっており、必ずしも開発経済学の新しい関心に向けた理論的な展開が十分とはいえない。著者はこうした状況に対して、文化と発展、地域発展、参加型発展などを重視する内発的発展論、社会構造と経済の動きとの関係を解明する構造学派の諸理論や社会、人間開発に関する諸分析を集め、そして整理しながら開発的発展論、社会的経済学、人間発展論を統合的に考えていく際の一里塚になればと願っている。これは人間中心の経済学を再構築するうえでも重要な挑戦といえるであろう。前回入賞の峯陽一著「現代アフリカと開発経済学」でも「現代の経済学はアフリカの社会を治め苦難を救うことにどれだけ貢献できるか」と述べている。 |  |
第4回受賞作品(平成12年度)
峯陽一著
|
|
| 選評 | |
| 「アフリカ社会を治めアフリカ民衆の苦難を救うために、現代の経済学はどんな貢献ができるのだろうか。そう考えるときアフリカの世界はむしろ経済学が鍛えられていく舞台として位置づけられる」。これが本書の全編を貫く思想であろう。そこからは地域研究家としてアフリカをこよなく愛してきた著者の学者魂がひしひしと伝わってくる。本書は初めに「歴史への視座」を設け、古代の輝き、奴隷貿易の傷痕をしっかり見据えた上で、ノーベル経済学賞を受賞したアフリカ系人のW.アーサー・ルイス(1979年)、アジア人のアマルティア・セン(1998年)、そしてアルバート・O・ハーシュマンという3人の経済学者をアフリカに登場させ、アフリカという透視鏡を通して彼らの仕事を実際に読み直しながら、3人の思想的営みの絡み合いを浮かび上がらせていく。著者は「3人の議論がある種の輝きを放っているとすれば、それは開発経済学の成熟期の輝きというよりも、発生期の輝きだといえるのではないか」と述べているが、これが本書の真髄でもある。苦悩と希望の歴史的な背景、農業問題、都市化、累積債務、構造調整、飢餓、地域紛争、開発、民主化、市場経済化の展望という多様なテーマをめぐり、現代アフリカの政治経済学を様々な角度から論じている。経済学に対しアフリカから檄を飛ばしているといえる。その意味で、国際開発研究に挑戦する21世紀の研究者への檄文ともいえる。また、これは故大来佐武郎先生の気概に合致した研究図書でもある。 |  |
第3回受賞作品(平成11年度)
中兼和津次著
|
|
| 選評 | |
| 本書は中国経済についての優れた教科書であるだけでなく、開発経済学についての優れた教科書である。同時に本書は中国経済についての優れた研究書(の解説書版)でもある。すなわち中国経済についての教科書といっても、本書は叙述的、解説的な内容に終始する入門書ではなく、開発経済学、体制移行論の視点からの分析的な内容を含む労作であり、研究書としても中国経済研究の先端をいくものとなっている。著者ははしがきで、著者による1992年の『中国経済論ー農工関係の政治経済学』を東京大学の講義に使ったところ、難しいという反応が学生の間から出たので、今回は学部の3年生以上を対象にしたと書いている。たしかに、いくつかの理論の解説なども挿入されており読みやすい。それでも、そうした理論が応用されていること自体が内容の高度さにつながっている。特定の発展途上国の分析に、開発経済学などの理論がこのように応用されうるということも印象的である。その意味で、開発経済学についての優れた教科書にもなっているといえる。また、経済理論の応用にこだわりすぎて重要な論点を落としたりはしていない。それどころか、多くの読者が知りたいであろう諸点について「政治経済学」的な議論もたっぷりと盛り込まれている。例えば、社会主義という枠組みに政府が囚われている故に市場経済への移行と経済発展をねらう政府の政策が大きな困難に遭遇している状況の議論や、中国経済が将来の世界に対して及ぼす影響や、日中関係を論じた部分などなどである。 |  |
辻村英之著
|
|
| 選評 | |
| 本書は、南部アフリカにおける潜在的失業状態を解消し、黒人大衆の絶対的貧困を解消することを同地域開発の最優先課題として捉えた上で、この状態をつくりだしている「未開発化圧力」「構造調整圧力」について分析を加え、これに対抗するためには、「黒人小農民が...自らの生活・生産を再生産していけるように、彼らの機能を高める」必要があることを指摘し、これができる農業協同組合を育成するための条件を明らかにしようとしている。著者は、理論面ではすでに古いとして捨て去られがちな従属理論を、研究対象に適合するように創造的に再解釈している。その枠組みの中で、構造調整政策の限界などについて加えている分析については、評価がわかれるが、ナミビアやタンザニアの経済を分析してその基本構造に迫ろうとしているなかで、本書の読者に新鮮なアイデアを提供してくれている。また、実務面ではこれまで失敗例ばかりの多かった協同組合重視の楽観論を批判しながらも、ナミビア、タンザニア、日本の協同組合を事例として、その育成を評価し、その内部の諸問題、例えば伝統と近代の相克について、検討を加えた上で、民主的意志決定機能や圧力団体機能を充実させる指導と教育を協同組合に期待している。著者は、こうすることで、構造調整政策のファースト・トラックの影響のもとで、マージナライズされている南部アフリカの黒人小農民セクターにおける開発のスロー・トラックの可能性を指し示している点で注目に値する労作である。 |  |
第2回受賞作品(平成10年度)
絵所秀紀著
|
|
| 選評 | |
| 本書は非常に優れた開発経済学のテキスト、教科書であることをまず特記すべきであろう。開発経済学の諸説を網羅する際に関連の経済理論もていねいに解説していることも、テキストとしての有用性を高めている。入門書としても使えるだけでなく、かなり高度の議論もとりあげているため、専門家にとっても役に立つ。また、本書は開発経済学の学説史としても非常にバランスがとれている。開発経済学の起源から最近の説まで漏れなくカバーしているというだけでなく、現在の開発経済学においてパラダイム転換が必要となった歴史的、理論的な背景がよく理解できるように記述されている。そして、現実との緊張関係の中で開発経済学が変動を繰り返すことを多くの例によって雄弁に示しており、「アイディアの展開史」という著者のねらいは、その意味で成功しているといってよい。著者が渉猟した文献の量も相当量にのぼり、本書はそれらへの体系的なガイドともなっている。「開発経済学のパラダイム転換」はコアの部分である第4章のテーマであるが、ここはよく読むとまさに「開発の政治経済学」になっている。「開発」という課題はすぐれて政治的なものであり、単なる経済学の一分野ではない、という見方はわが国の開発援助にたずさわる人たちからもしばしば聞かれる声である。しかし、それがこのような理論的、学問的な形で示されたのは初めてではなかろうか。さらに、アマルティア・センの「潜在能力」アプローチを開発の実践、及び政治経済学での新しい地平を切り開くものとして位置づけていることが、本書のメッセージを明確にしている。 一見すると単なる学説史、入門書に見えるが、よく読めばそうではない。熟読玩味に値する一冊であろう。 |  |
深川由起子著
|
|
| 選評 | |
| 大来賞は「国際開発研究」という言葉が冠されているので、表題から見ると単なる一国経済論にみえる本書が対象になりうるのか、という疑問もあるかもしれない。そうした疑問に対しては、「本書はもちろん非常に優れた韓国経済論であるが、といって単なる韓国経済論にとどまってはいない」という答が可能である。これは、著者が青木・奥野モデルを韓国に適用しようとしていることなどから明らかであろう。青木・奥野モデルは、大雑把にいえば、同じ資本主義システムであっても経済内部のシステムは多様でさまざまな資本主義がありうる、それぞれのシステムはそれぞれの状況に応じて自然発生的にできてきたものだから、それぞれメリットを持っているという考え方である。本書はこの青木・奥野モデルを援用しつつ韓国経済の解明に努めている。明示的にこのモデルについての言及がない場合でも、日本経済との比較が行われているところなどで、このモデルが意識されている。この「多様な資本主義がありうる」という考え方からすれば、多様な経済発展、開発がありうるということになる。本書は、どのような発展モデルが有効かという問に対して、韓国モデルも一つの答であったということによって開発経済学の一部になっているのである。ただ、著者は過去において有効だったものが最近において行き詰まりにいきつく理由を分析することを本書の中心テーマに据えているので、以上の点は見落とされやすいかもしれない。読者は、この行き詰まりの分析が本書完成後の韓国経済の危機を見事に予言していたことに強い印象を受けるであろうが、この点のみに目を奪われなければ、本書が開発経済学との関連からも高く評価できることに気がつくであろう。 |  |
第1回受賞作品(平成9年度)
廣瀬昌平・若月利之編著
|
|
| 選評 | |
| 西アフリカの農業開発にアジア的な水田耕作を導入する可能性を探った学際的・実践的研究書である。本書は、西アフリカの深刻な食料・環境危機の原因の根を、欧米諸国の奴隷貿易によるアフリカ社会の破壊と植民地体制下での伝統的農業システムの破壊ととらえ、農業生産性を向上させ、環境保全を行いつつ集約的な持続的農業を展開するための戦略として、アフリカの伝統的稲作に、アジア的な肥沃度持続型の水田農業を融合させようという思想が根幹をなしている。生態環境や伝統的農業、土地利用システムに関する調査、近隣牧畜民に関する生態人類学的調査等を基礎資料としたうえで、ガザ村において農民参加による水田開発や灌漑管理、魚の養殖アグロフォレストリーのオンファーム実証研究を行い、評価には農民の批判を受け入れて結論を引き出している。日本が得意とする水田農業の分野で、アフリカの伝統農業と調和できる「アフリカ型水田農業」を目指すべきとのメッセージは、我が国の援助政策にとって重要な意義を持つと言えよう。 |  |
原洋之介著
|
|
| 選評 | |
| 開発経済学の理論を要領良く紹介したテキストブックである。著者自身が巻頭で述べているとおり、開発とは「社会変化を伴う多面・多元的な過程であり」、開発経済論のテキスト執筆においては、テーマの選定とその論じ方に関して「書き手の問題意識が直面に顕在化せざるを得ない」。本書における書き手の問題意識は市場の存在を当然の前提としている経済成長論への批判、そして市場そのものの発展過程の解明という挑戦となって顕在化している。画一的な自由経済理論の押しつけに対して、国の歴史文化の独自性に注目している点が審査委員の共感を呼んだ。「開発途上国では、市場の制度が確立されていないから、新古典派的な経済学があてはまるとは限らない」という視点を含め、国際開発の中での経済学の位置付け、新古典派理論そのものへの挑戦という今日の重要な課題に果敢に取り組む姿勢を高く評価した。 |  |